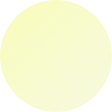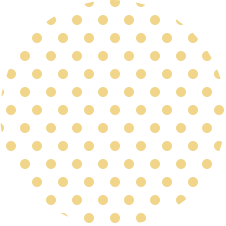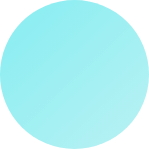Vol.16
福祉を学んだからこそできる、
お客さま一人一人の心に寄り添った温かいサービスを平等に。
坂下 果歩さん
ANA大阪空港株式会社
2023年卒業社会福祉学科
京都府出身。人が好きで人と関わる分野に興味があったこと、オープンキャンパスで美しい校舎や明るい学生の姿に引かれたことから、人間福祉学部社会福祉学科に進学することを決意。「ソーシャルワーク実習」や児童養護施設でのアルバイト、教員やゼミ仲間との交流を通じて「誰かのために」という心を育んだ。現在は、空港で旅客ハンドリング業務に携わり、一人一人に寄り添う接客を心がける。
人から人へ心を温かくするサイクルができれば。
印象深かった授業の一つが、「ソーシャルワーク演習」です。支援を必要としている人から話を聞く機会が多く、中でも薬物依存の方の姿に、過去に何があろうと人は誰かの支えがあればまた前を向いて生きていくことができると気付かされ、同時に支えている周りの人たちの温かさに感動を覚えました。3年生時の「ソーシャルワーク実習」では大阪市内の特別養護老人ホームで約1カ月間、入居者さんのお世話をしたり、ソーシャルワーカーとしての働き方を見せていただいたりしました。私は、コロナ禍で人と接する機会が減り笑顔が少なくなっていく入居者さんのためにレクリエーションを提案し、一緒にマジックやクイズを楽しみました。最初のうちは注目してもらえませんでしたが、自分のやりたいと思う気持ちを丁寧に伝えることで、徐々に参加していただけるようになりました。「その人のために」という強い思いは、表情や話し方、態度など全てから伝わるのだと実感しました。
また、3年生の秋から卒業まで、児童養護施設でアルバイトとして夕食の準備や入浴の手伝いなど日々の生活のサポートをしました。子どもたちはそれぞれ性格が異なり、求めていることも違います。私にできたのは、アドバイスなどではなく、心が温かくなればいいなと思いながら抱きしめることでした。そうすることで怒りっぽい子どもが徐々に穏やかになっていく様子を見て、自分が温かさを与えることでその子がまた他の誰かに温かさを伝える、そんなサイクルができればいいなと思いました。

自己肯定感が人の幸せにつながっているのか。
社会福祉の歴史と思想、在日外国人高齢者ソーシャルワークを専門とする李善惠教授のゼミで2年間学びました。李先生には、「キリスト教と福祉」の授業や「ソーシャルワーク実習」の発表などで関わらせていただき、突き詰めたい分野が見つからず悩んでいる私に「これから一緒に探していこう」と言ってくださったのが選択の決め手になりました。
卒業論文のテーマは「自己肯定感が就職活動に影響するのか」です。自己肯定感に着目したのは、特別養護老人ホームや児童養護施設で年齢を問わずさまざまな人と接する中で、自己肯定感が人間の幸せにつながっていると思われる場面がよくあったからです。「自分は必要ない人間だ」と発言する子どもに、自分のことをもっと認められたら前向きに生きられるのではないかと感じたもの一例です。自己肯定感は、人からの評価や他人との比較で高くもなれば低くもなる一面がありますが、自分の良い点も悪い点も全て受け入れられた時にこそ真の自己肯定感を得られるのではないかと私は思っています。論文作成に当たっては、李善惠教授と相談してアンケート方式に決め、社会調査やデータサイエンスを研究する李政元教授にアンケートの取り方や集計方法を週1回、一対一で教えていただきました。先生方と学生との距離が近い人間福祉学部だからできたことです。

「人のために動く」ことが人生の目標になった。
大学入学前は、福祉イコール高齢者、介護というイメージが先行していましたが、児童、障がい者など多様な領域があり、いろいろな事情を抱えた人たちがいること、「助けて」と言葉に出せないけれど支援を求めている人たちがいることが分かりました。人間福祉学部では、学科の枠を越えて興味のある科目を受講できることが特徴で、私は高校、大学とソフトボールをしており、運動に合わせた適切な栄養摂取についての知識を習得する「スポーツ栄養学」は興味深かったです。また、人をじっくりと観察して、「この人はこういう発言をしているけれど、心の中ではこう思っているんじゃないか」などと思い巡らすのが好きだったので、「心理学」の授業では人間の心理と行動の関係などを楽しく学べました。見ている世界がどんどん広がっていく感じでした。
4年間の学びを終えて、福祉は人に寄り添い、相手のためにできることを考えて行動するという優しい世界だと改めて思いました。先生方をはじめ、同じ授業を受けている仲間やゼミのメンバーには、「その人のために」「誰かのために」という温かい気持ちを持った人が多く、私自身も人のために動きたいと思うようになり、それが人生の目標になりました。

お客さまの状況に合わせた“最適な”サービスを。
就職活動は、福祉業界か一般企業かで迷いましたが、一般企業に入り、より多くの人と関わって自分を成長させたいと思い、小さい頃から憧れていた航空業界にチャレンジしました。現在は、ANA大阪空港株式会社の旅客スタッフとして、大阪国際空港で搭乗手続きなどのカウンター業務や、搭乗・到着案内といったゲート業務、さらにロビーでのお客さま対応などに従事しています。
心がけているのは、全てのお客さまに平等に、それぞれの心にそっと寄り添えるような温かなサービスを提供することです。そこには、「一人一人の異なる状況に合わせた、最適な支援を考える」という社会福祉学科での学びが生きています。お客さまの中にはあまり話しかけてほしくない方もいれば、いろいろお話されたい方もいらっしゃるので、その方の表情や口調から心情を読み取り、福祉分野で学んだ人間だからこそできる寄り添い方を常に考えています。ある時、危篤状態のご家族のもとへ急ぐお客さまが、搭乗するはずの飛行機に乗り遅れて涙されるということがありました。少しでも早く目的地に到着するため地上交通も含めてさまざまなご提案をした結果、納得のいく方法で出発していただくことができました。悲しみの中にありながら最後に感謝の言葉を残されたことが、今も心に残っています。逆に厳しいお言葉を頂くこともありますが、そういう時も、授業で教わった「人それぞれ行動や言葉には背景がある」ことに思い至れば、納得して受け入れられます。

大学での学びをいつか子どもたちに還元したい。
ゼミ時代の友達とは時々会って近況報告をし合っています。彼女は地方公共団体で生活保護担当として働いており、話を聞くたびに壮絶な世界だなと感じます。私は現在の会社で、目の前の一つ一つの仕事に一生懸命に取り組みつつ今の立場でできること、大学での福祉に関する学びを還元できるようなことをやっていきたいと思っています。あくまでも個人的な希望ですが、この業界にいる人間として、あまり旅行などに行くことがない児童養護施設の子どもたちに、飛行機を見てもらったり体験で乗ってもらったりする機会をいつか提供できればいいなと夢見ています。
就職活動中、「本当に就職できるのだろうか」と不安になり、李善惠教授に相談に行ったことがあります。その時に、「あなたの笑顔は人を穏やかにするし、ほっと安心させてくれます。だから、面接で緊張していたとしても笑顔でいることを忘れないで」と、アドバイスしていただきました。お母さんのような存在の方で、私のことをずっと見てくれているんだなとうれしかったです。旅客スタッフの仕事も、表情はとても大事です。李教授から頂いた言葉を大切に、毎日、口角を上げて頑張っています。