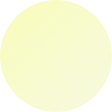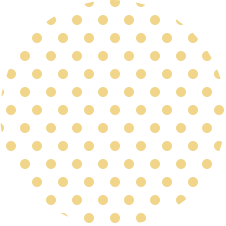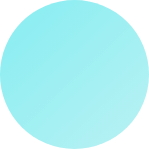Vol.23
わたしたちが育った家庭、
共に育てる家庭―こども虐待を考える新たな視点
畠山 由佳子教授
いろいろな家族といろいろな家庭
皆さんが育った家庭ってどんなところでしょうか?私たちが「家庭」を考えるときにその基準となるのは自分が育った家庭です。「家庭」は人が生まれてすぐに初めて出会う環境、言うならば初めて出会う「世界」です。小さなこどもにとっては「家庭」は世界のすべてであり、さらに広い世界へ踏み出していくための大切な「基地」にもなっていきます。ただ蓋を開けると、私たちみんな育ってきた家庭は様々、家族も実は様々です。家族といえども一人ひとり違う人間なので、その集合体である「家族」もみんな同じではありません。血縁や婚姻関係を持つ人たちが「家族」として認識され、「家庭」という環境を構成している場合もあればそうでない場合もあります。家庭のかたちは1つではなく、一見同じように見えてもそれぞれの家庭がもっている「文化」や「習慣」「ルール」は実は異なります。

「バスタオル」の話
家庭の文化の違いを話すときに、私が例としてよく出すのは「バスタオル」です。バスタオルの話って何?と皆さんは思われるかもしれません。お風呂に入った後、身体を拭くバスタオルは皆さん、ひとり1枚ずつ使いますか?それとも家族で共用しますか?私の家はひとり1枚バスタオルを使う家で、世の中の家はみんなうちと同じだと思っていました。私は高校生の時に友達の家に泊まりに行って、そこのおうちはみんなで1枚のバスタオルを共用するのを知ってとてもびっくりしました。「だって、お風呂に入ってきれいになった後なんだから、汚くないよ。それにひとり1枚使っていたら洗濯物が大変やん」と友達はびっくりしていた私に言いましたが、確かにそういう理屈もあるなぁと納得しました。
この違いは「いい」とか「悪い」とかではなくて、それぞれの家庭の文化の違いです。同じように毎日の日課や決まりごと、行事や習慣、何が大事かなどの価値も家庭によって様々です。ともすれば、それは何世代にもわたって継承されている場合もあります。
家庭は家庭の数だけ様々であり、そのあり方は尊重されるべきですが、時に、弱い立場の人たちにとって家庭が安心・安全でない場所になることがあります。家庭内で起こっていることは外からはわかりづらく、特に日本では親の持つ権利(親権)が社会的にも法的にも強い力をもっているため、これまで公的機関は家庭内に介入することに躊躇していました。結果、こどもがひどく傷ついたり、時にはかけがえのない命を失ってしまったりすることがありました。
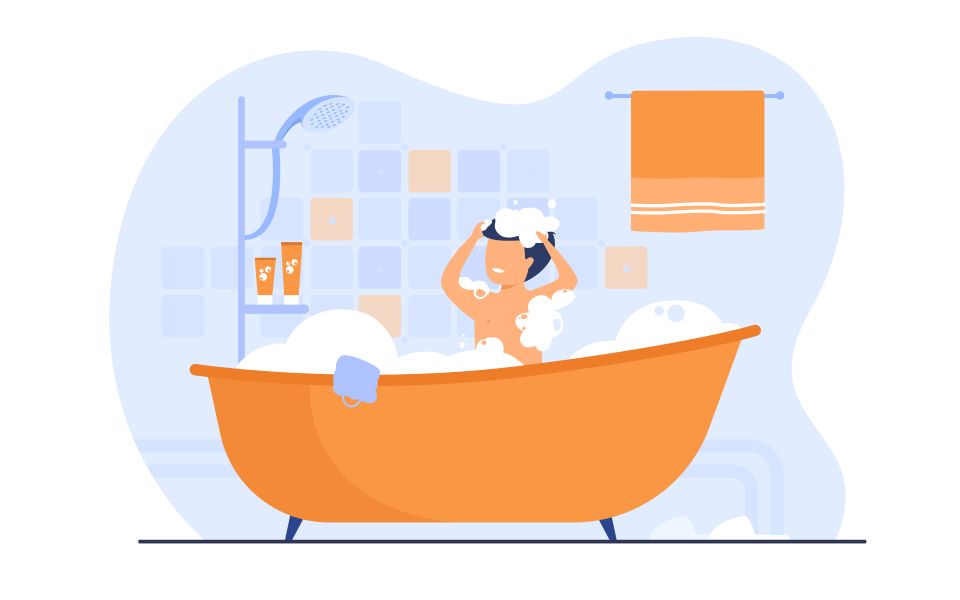
「心配な家庭」に必要なのは「虐待している」と呼ぶことではない
2000年に児童虐待防止法が制定されるまで、こどもの相談機関である児童相談所は強制介入のための法的手段がなく、こどもを守るため四苦八苦していました。児童虐待防止法は法的に「児童虐待」を定義し、その早期発見・早期介入のための「通告制度」を作り上げ、児童相談所が積極的に家庭に介入してこども達を救うことができる権限を与えました。
しかし、社会の児童虐待に対する認識が高まるにつれ、児童虐待として対応されるケースはどんどんと増え続け、「緊急度・重症度の高いケース」だけではない様々な家庭が含まれるようになりました。その中には、親自身が心や身体に病気や障がいがあり、周りが適切だと思う子育てが十分できない家庭や、親が仕事を失ってお金がない家庭や、養育者である大人が1人しかいないので心身共に余裕のない家庭などが含まれていました。これらの家庭は「虐待」というよりは周りが「あの家庭、大丈夫かな」と心配になっている家庭です。それなのに「虐待(の疑いのある)ケース」として全部一緒くたに対応されています。これらの家庭に本当に必要なのは周りから「こども虐待の疑いのある家」と呼ばれることでしょうか?
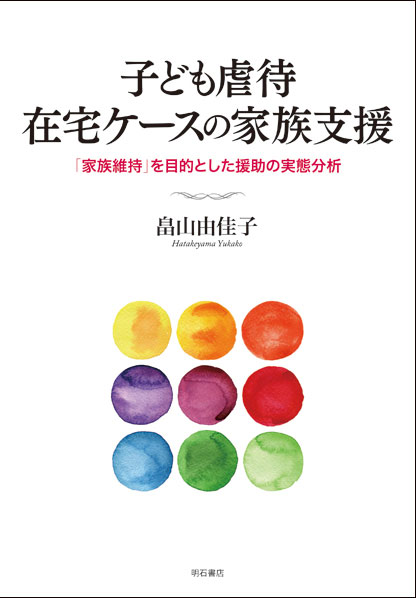
こどもたちが大人になることを楽しみにできる社会を目指して
私は学生のころから、どうすればこどもたちの安全安心な暮らしを家族と共に作っていけるのかということを考えてきました。他の国ではどんな風にこどもの安全を社会が守ろうとしているのか知りたくて、アメリカ合衆国やフランス共和国での調査も続けています。パーフェクトなシステムは世界中のどこにもないのですが、国際的に比較することで様々なヒントを得ることができます。
私は地域が大きな家庭となり、こども達を地域のいろいろな家庭と共にみんなで育てるような実践や体制をいかに作っていくのかを考えることこそが、最終的に「こども虐待」を予防することになると思っています。だからこそ、実際にこどもや家庭を支援している市町村の人たちや民間団体の人たちと一緒に、より良いこども家庭支援のあり方を考え続けています。本当の主役である家族のみなさん(親もこどもも)と一緒に考えていくことができる仕組みについても取り組んでいます。
これからの社会を作っていくのは若い世代の皆さんとこどもたちです。皆さんのようなソーシャルワークに興味を持つ若者たちに、「こどもたちが大人になることを楽しみにできるような社会」をぜひ作っていっていただきたいです。こどもたちの明るい将来を目指すためにあるのがこども家庭ソーシャルワークです。人間福祉学部で学んだソーシャルワーカーがこども家庭支援領域でたくさん活躍してほしいと願っています。