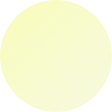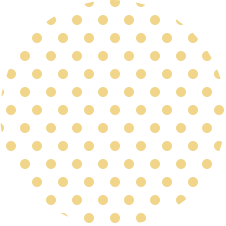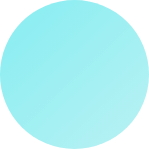Vol.17
病棟保育士となって
病床の子供に寄り添い、
生きる希望を一緒に探したい。
的場 満希さん
人間科学科
伊丹市出身。子供に関わる職に就きたいと聖和短期大学(現関西学院短期大学)に入り、実習をきっかけに病棟保育士を目指す。2年間で幼稚園教諭と保育士の免許を取得後、生と死を考え、死別による悲嘆とそのケア等を学ぶため人間福祉学部人間科学科に編入。親を亡くした子どもたちのグリーフケアを行うレインボーハウスでフィールドワークを重ね、卒業論文は「子どものグリーフケア」をテーマに取り組む。
編入して死別による悲嘆やそのケアを学びたい。
聖和短期大学を卒業して人間科学科に編入したのは、病棟保育士になる夢をかなえるためです。病棟保育士は、入院している子供たちのお世話をするのが仕事で、特に私は、余命宣告された子供が病棟で過ごす期間、死と向き合う中で前向きに生きられるように保育士としてサポートしたいと考えています。きっかけは短大時代、児童発達支援センターでの施設実習を通して障害があったり病気だったりする子供たちがもっと生きやすいように支えたいと思ったこと、病棟保育士をしていた先生の授業で仕事内容やエピソードを聞いたことでした。性格的に、大勢に対するよりも、一人ひとりと密に接し深く関わる仕事が向いているとも感じていました。短大の2年間は幼稚園教諭や保育士になるために子供の成長や発達を学び、編入後は、病棟保育士として必要な分野、例えば、死別による悲嘆や、それをケアするグリーフケアについて学んでいます。
卒業単位数を修得するため、現在は毎日フルに授業を受けており、将来に向けて充実した時間になっています。「悲嘆学」や「グリーフケア論」などは人の本質的な感情の部分を扱う授業で、一方でそれと対照的な、法律や制度、専門職の役割といった授業も受けています。両方をバランスよく学ぶことで幅広い知識が得られ、基本となる知識を持った上でグリーフを抱えた個人個人に寄り添う保育士になれるのではと思います。

望んでいた授業を受け掲示板で仲間の意見を知る。
死別後の悲嘆とそのケアなどをテーマに研究されている坂口幸弘教授の授業は、3年生の春学期に「悲嘆学」を受講し、秋学期には「グリーフケア論」を受けています。いずれも、私が最も学びたかった内容で、子供の悲嘆について学習し、その悲嘆に対するケアを受けないで死別の経験を抱えたまま大人になった場合にはどういう傾向が見られるのかを知ったり、悲しい記憶をわざと思い出して自分の心の整理をしていくといった実践的なケアの方法を身につけたりしています。スピリチュアルケアや高齢者の終末期のケアなどを研究分野とする市瀬晶子准教授の「エンド・オブ・ライフケア論」では、病棟で死を目前にした成人患者たちが、生きるということに前向きに、残りの人生をどれだけ充実して過ごせるかに関してがん看護専門看護師の方の実践の動画を視聴し、実践の様子から学ぶ機会もありました。深いところまで掘り下げられた授業内容は望んでいた通りのものでした。
また、坂口教授の授業では受講後の感想を書く掲示板があり、他の学生のコメントも見ることができます。例えば、ある日の「グリーフケア論」では、私が「人間科学フィールドワーク」でお世話になっていた、親を亡くした子供たちが集う神戸レインボーハウスの方がゲストスピーカーでした。その時の掲示板を見ると、「子供とフラットな関係性を持ち対等な関わり方をするのは、日常生活ではなかなかできない」という私と同じような考えもあれば、「子供が小学校や中学校に上がった時のことを考えると、専門機関と連携する方がいいのでは」といった意見もあり、他の人のさまざま視点からの感想を知ることができました。
子どものグリーフ表現は悲しみだけでは無い。
「人間科学フィールドワーク」では当初ホスピスを希望していましたが、コロナ禍でかなわず、3年生の6月から12月まで、神戸市にある神戸レインボーハウスで活動しました。親との死別という共通の経験をした子供たちを対象に、月2、3回日曜に実施されるワンデイプログラムと、宿泊プログラムを実施しており、私は養成講座を受けて子供を手助けするボランティアとして参加しました。子供の表現方法は言葉ではなく遊びです。遊びの中で悲しさを表したり、怒りを発散したりします。スタッフの方から教わったのは、子供の行動を見てこちらが勝手に評価しないということ。例えば、サンドバッグを何度も殴っている子供には、「めちゃくちゃ怒ってるね、どうしたの?」ではなく、「めちゃくちゃ殴ってるね、どうしたの?」と声をかけ、「学校で嫌なことがあった」「楽しいから殴っている」と理由を引き出すような関わり方が大事だとアドバイスいただきました。子供たちは一人ひとり性格も背景も、感じ方も異なり、実際に向き合ってみて初めて分かること、学ぶことがたくさんありました。父親を亡くしたある少女は、小さい頃、父親に理不尽に怒られたことをずっと覚えていて、「嫌いな感情だけはある」と正直に話してくれました。子どもが亡くなった親に感じるものは悲しみや喪失感だけでは無いのだと、大きな衝撃を受けました。
このフィールドワークは、人間科学科生のみが受講できる授業です。長期間の実習というだけではなく、エピソード記述の作成、中間報告や最終報告を経て、最後は冊子にまとめるという大変な作業もありますが、編入目的の一つを成し遂げ、実践ならではの学びを得ることができました。

学びを言語化することで自分の中に落とし込めた。
ゼミは、市瀬晶子准教授のもとで学んでいます。人生の終末期について研究されているので、終末期を迎えた人との関わり方を学びたいと思い選択しました。市瀬准教授は「人間科学フィールドワーク」を担当されており、「学びを言語化することが大切。文字にして伝えることで学びが深まる」と常々おっしゃっています。フィールドワークで印象に残った場面を書きとめるエピソード記述はとても大変で、「この言葉は分かりづらいので表現を変えて」「どういう心の動きがあったのかを付け加えて」などとアドバイスを受け何回も書き直しました。自分を客観視して言語化する作業を通じて、「私はこういうことに関心があり、こんな心の動きがあって、このことを学べた」と、フィールドワークでの経験を自分の中にしっかりと落とし込むことができました。
卒業論文のテーマは「子どものグリーフケアについて」です。神戸レインボーハウスにはグリーフケアのプログラムがありますが、参加していない子供もいます。その割合がどれくらいで、なぜ参加しないのかに着目しており、今後は、そういう子供たちが自らの経験やグリーフをどう捉えているのかといった点を深掘りしていきたいと思っています。個々に話を聞くことはもちろん、スタッフへのインタビューも考えています。現在のボランティアの中には、当事者として小学生の時から神戸レインボーハウスを訪れプログラムに参加していた人もいますので、当時の記憶やボランティアになった理由なども聞き取っていく予定です。

それぞれが違う進路を描く大学で将来に一歩近づけた。
編入して1年がたち、病棟保育士になりたいと漠然と考えていた頃に比べて自分の将来に一歩近づけたかなと感じています。死別による悲嘆やそのケア、子供の感情などについて学び、どういうふうに関われば子供の気持ちに寄り添えるのかが分かってきました。最終学年では、死を含めて生きることを考える学問「死生学」の授業を受けるつもりです。自分自身の死生観、死についてどう感じているのかを知ることができるのではないかと期待しており、それは人をケアする上でとても大切なことだと考えています。
卒業後は、まず幼稚園教諭として何年か経験を積み、最終的には病棟保育士として働きたいと思っています。幼稚園教諭としては神戸レインボーハウスのボランティアのようにフラットな関係性で子供たちに向き合い、彼らがありのままの姿で関われるような存在でありたいです。また、病棟保育士としては、死が身近にあり生きる意味を見失ってしまった子供と一緒に、生きる希望や生きる意味を探し、残りの人生を楽しく充実したものとし、生きてよかったなと思ってもらえるような関わり方を目指しています。
幼稚園教諭や保育士という同じ目標に向かってみんなで一緒に頑張った短大時代と異なり、大学ではそれぞれが違う将来を思い描いています。同じゼミでも学びたいことは異なっており、その発表を聞くだけでもこれまで知らなかった知識を得られます。いろいろな世界を見ることができ、楽しみながら刺激をもらっています。