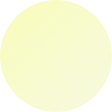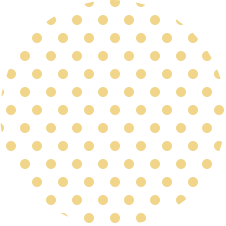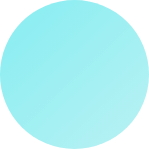Vol.21
フィールドに出よう!-越境体験のすすめ
森重 裕子助教
社会起業学科
「インターネットやテレビ、文献の情報だけで分かった気になってはいけない。フィールドに足を運んで初めてわかることは多い。ぜひ、フィールドに出てください。」
これは以前、ある国際会議に参加した際、シンポジウムに登壇していた世界的に著名な医学研究者2名が、会場の高校生に向けて口をそろえて述べた言葉です。思えば、私自身も人生が大きく変わったきっかけは、初の海外渡航であった大学の卒業旅行、ネパール訪問でした。
ネパールでは、穏やかで親切な人々や美しい景色、おいしい食べ物など、多くの素敵な出会いがあった一方で、一番心が動いたのは、ストリートで眠る子どもたちの姿でした。今ではあまり見かけることがなくなりましたが、当時はたくさんの子どもたちが路上にいました。もちろん、そういう子どもたちが存在するということは知っていました。でも、現場で実際に出会って言葉を交わしていくうちに、彼らの存在が「自分の世界のこと」になっていきました。子どもたちが眠る埃っぽい道端や行きかう人々の様子、彼らなりに安全に心地よく眠る工夫、昼間に各国語でツーリストに明るく話しかける巧みさ、たばこや大麻、有機溶剤を吸っているときの匂いや足つき、大人びた厳しい表情と子どもらしい屈託のない笑顔…
帰国後、百貨店に就職しましたが、生まれた場所が異なるだけで、こんなに違う人生を歩んでいる子どもたちがいることをずっと考え続け、とうとう7年後に会社を辞め、関西学院大学の大学院で子ども家庭ソーシャルワークを学び始めました。その後も、「予防」に関心を持ったことから公衆衛生/社会疫学を学ぶために医学研究科に進学した他、ネパールから西アフリカのブルキナファソに研究フィールドを移したり、「エンパワーメント」に関心を持ってコスメや手工芸品の事業で起業したり、NGOの現地代表としてプロジェクトを企画・立案・運営したりするなど、思えば多く「越境」してきました。

2014年のシアバター買付け時の様子(現在は治安悪化で行けなくなりました)
分野にせよ、場所にせよ、越境するということは、なかなか大変です。たくさん勉強する必要があったり、新しい場所や人間関係、やり方に慣れたりしなければなりません。一方で、越境することで自分自身への理解を深め、柔軟性や主体性、多角的な視点を獲得できるなど、多くの学びがあります。より自分の輪郭がくっきりする感覚とも言えるかもしれません。自分の中に比較軸を持つともいえるでしょう。特に予測不可能な未来を生きるみなさんには、今後の人生をよりよく生きるために大切なものを得る機会となるに違いありません。
また、越境体験の中でもフィールドに出て、新たな人やコト、モノに出会うことは、成長を加速させてくれます。今までの慣れ親しんだ環境、いわゆるコンフォートゾーンから出て、全く異なる環境で活動すると、多くの場合、困惑や違和感、時には葛藤や拒絶を生みます。しかし、次第にその中から自分の価値観や限界、得意なことや可能性などを見出し、新たな価値観や知識、能力を獲得してゆくようになります。このようなエンパワーメントの効果は、さらにその経験を自分の言葉で人に伝えることで強化されます。
私の研究は、「女性」と「参加」、「エンパワーメント」で表すことができます。私自身が日本社会で女性として感じてきた違和感や理不尽さへの怒りのようなものを、ネパールやブルキナファソの女性たちにも見出し、共感し、共有してきたことが、今までの研究や活動の根本をなしているように思います。境界を越えたフィールドで出会った女性たちと、彼女たちが直面している課題の解決に向けて一緒に活動するうちに、それらは自分が属してきた社会に存在するジェンダー課題が形を変えて表出されてきたことだと気づかされました。そして、彼女たちと活動を共にすることで、当事者として参加することによるエンパワーメントを目の当たりにし、そのことを研究している中で、気付かないうちに自分も女性当事者として、そのエンパワーメントの恩恵を受けてきたように思います。

ごみのリサイクルを見学する(人間福祉海外フィールドスタディ、ネパール)
私が担当する多くの授業は海外へ渡航するプログラムで、カナダでの「社会起業中期英語留学」や、ルワンダに2週間ほど渡航するグループ・スタディツアー「社会起業フィールドワーク(海外)」、ルワンダやネパールなど様々な国で200時間の活動を行う「人間福祉海外フィールドスタディ」などがあります。すべてのプログラムでは事前学習があり、帰国後、口頭で報告する機会があり、報告書を書きます。渡航中も担当教員や学部事務室、受け入れ先のみならず、プログラムによっては実践教育支援室や現地非常勤講師などのサポートがあります。「フィールドに出る」という越境の際の負担を調整し、できるだけリスクをなくし、学びを深めて成長につなげる環境を作るべく計画されています。もちろん、フィールドは海外でも国内でもよいのです。人間福祉学部は、ソーシャルワークやスポーツ・健康科学を基盤として作られた経緯から、フィールドでの実践を大切にしています。また、関西学院大学自体が、学生が活躍できる機会とフィールドをたくさん用意しています。学生時代のうちに、ぜひ、フィールドで深い越境体験をしてみてください。

インクルーシブ教育の学校で教える学生(人間福祉海外フィールドスタディ、ルワンダ)
※写真はいずれも筆者提供
※所属や内容は掲載日時点のものです。また内容は執筆者個人の考えによるものであり、本学の公式見解を示すものではありません。

足踏みミシンの使い方を教えてもらう(社会起業フィールドワーク(海外)、ルワンダ)